![]()
JR東日本
本系列は、JR東日本のユーザー(利用客)アンケートを反映し、さらに車両の信頼性を向上させて輸送障害を防ぐため、従来の同社の通勤形・近郊形車両と比べると全体的に「ゆとり」を持たせた設計として、利用者が快適に乗車できるように配慮されている。開発にあたっては、車両の信頼性向上と乗客へのさらなるサービス向上を目指し、以下の項目を基本コンセプトとした。
1.故障に強い車両(輸送障害の低減)
2.人に優しい車両
3.情報案内や車両性能の向上
4.車体強度の向上
車体構造
車体構造はE231系などと同様の軽量ステンレス製車体であるが、本系列では側面衝突事故時における安全対策を強化しており、側構体と屋根構体の主要な骨組みの位置を合わせ、これらを強度に結合させる「リング構造」を採用することで、万が一の衝突事故時における安全性を確保した。
車体幅については混雑緩和のため、2,950 mm 拡幅車体を採用している(2000番台を除く)ほか、床面高さを 1,130 mm(E531系と同じ)としてE231系よりもさらにホームとの段差を減少させた。普通車の客用ドア配置はすべて片側4か所である。
前頭部は踏切事故などにおける安全対策から、E217系以降の近郊形で採用した衝撃吸収構造を通勤形にも取り入れた。これは「つぶれること」で衝撃を吸収する「クラッシャブルゾーン」と「強固な構造」で前部を保護する「サバイバルゾーン」で構成される。これにより、大型トラックなどと衝突した場合にも、乗務員と乗客への安全性が向上した。
前照灯はHID灯とし、尾灯とともに窓上に設置した(2000番台を除く。同車は通常の前面強化構造で、前照灯は窓下配置のシールドビーム式である)。JR東日本では、これまでの車両について側面の客用ドア外側にカラー帯を配していなかったが、本系列では線区に合わせた色の帯(中央線快速の0番台の場合はオレンジ色)を配した。
E231系の2002年(平成14年)以降製造車(東京地下鉄東西線直通用の800番台を除く)では車外スピーカーの設置準備工事が行われていたが、本系列では製造当初より車外スピーカーが設置された。これはE531系で採用されたものと同一であり、東洋メディアリンクス製の発車メロディも鳴る仕組みになっている。これにより、発車メロディなどを導入していない駅でメロディを流すことが可能となった。メロディ終了後には「扉が閉まります。ご注意下さい」の乗降促進放送が流れる(2000番台では「ドアが閉まります。 ご注意下さい」になっている)。
行先表示器にはJR東日本の車両で初めてフルカラーLED式を採用した。車体側面の表示器は2段表示も可能で、始発駅では停車駅をスクロールで下段に表示させ、途中駅では次の停車駅を下段に表示させる。また日本国有鉄道(国鉄)から継承した車両や従来のJR東日本の通勤・近郊形車両(211系やE231系など)は、普通列車(各駅停車)の場合、車体側面表示器での種別表示を省略していたが、本系列においてJR東日本で本格的に普通列車(各駅停車)の場合でも「普通」(各駅停車の場合は「各駅停車」)と種別名を表示するようになった。
普通(各駅停車)表示時の背景色はラインカラーに準拠して各番台で異なる。0番台は黄色、1000番台は明るめの青色、2000番台はエメラルドグリーン(やや明るめの緑色)、3000番台は深めの緑色、5000番台は青色である。5000番台は種別表示を上段:京葉線(ワインレッド)、下段:種別とし、201系、205系の幕式側面表示器に引き続き武蔵野線との誤乗防止や内房線・外房線内からの総武線経由の電車との誤乗防止を促している。
乗務員室
運転席(0番台)
衝撃吸収構造の採用のため、乗務員室内はスペースが広く確保されている。運転台筐体や運転士用の座席をE231通勤形よりも 185 mm 高くした高床構造を採用し、前方視認性の向上を図っている(2000番台は通常の広さで、高床構造ではない)。計器盤は計器類・表示灯を廃し、これらを3枚の液晶モニターに表示するグラスコックピット構造である。主幹制御器は左手操作式のワンハンドルマスコンである。
前面ガラスのワイパーは常用の2本式に加えて補助ワイパーを設置し、故障時には切り換えることで補助ワイパーを使用する。
乗務員室背面仕切部は運転席背後を「非常救出口」とし、中央に遮光幕付きの大窓、右端に仕切扉窓を設置する。
車内内装
客室内装はユニバーサルデザインの採用やバリアフリーの向上、快適性の向上を目指したものとした。基本的な構成はE531系をベースとしたもので、車内はモダンで暖かみのあるカラーデザインとした。
内装の艤装工法についてはE231系やE531系までの艤装方法とは異なり、メーカーを問わずパネル式に統一された。ただし、川崎重工業製のE231系やE531系までの車両で見られたパネルを止める天井部のビスは、本系列では見えない工法になっている。
内装のカラーリングは白色をベースカラーにし、床敷物は茶色系の砂目柄入りとした。座席モケットの色柄は路線によって異なるものである。座席構造は209系以来の片持ち式バケット構造であるが、1人あたりの座席幅がE531系と同一の 460 mm(201系は約 430 mm、209系は約 450 mm)に拡幅され、座席自体も座布団の厚みをアップさせたほか、クッション材にSバネの入った柔らかいものに改良された。
客用ドアの客室側は車両間の貫通扉を含めて、従来のJR東日本の通勤・近郊形電車の標準であったステンレス無地から、白色化粧板仕上げとされた。客用ドアの窓ガラスは結露対策として四隅が角ばった複層構造を採用した。このドアの戸先部と出入口部の床面には黄色の警戒色を配し、目立たせている。このほか、ドアの開閉に合わせてドアチャイムの鳴動とドア開閉表示灯の点滅機能を装備する。
ドアエンジン(戸閉装置)は番台区分によって異なり、スクリュー軸駆動式とリニアモーター駆動式の2種類がある。各番台区分とも片側4扉のうち3扉を締め切ることができる「3/4閉機能」スイッチを設置するほか、0番台と3000番台については車内外のドアスイッチを乗客が操作することで開閉を行う「半自動機能」を有する。
車両間の貫通扉はE231系では2両 - 3両に1か所程度の設置であった(一部車両を除く)が、本系列では各車両の両端部の設置に増設され、扉は傾斜式戸閉機構を採用した。
袖仕切り部や座席間の握り棒は使いやすさを向上させるため、通路側にカーブした形状をしており、立っている乗客や座っていた乗客が立ちやすいように配慮した形状とした。座席上部にある荷棚はアルミ製の板状のものに、つり革は黒色の二等辺三角形状のもので、これらはE531系で初採用されていたものである。
側窓ガラスはいずれもUV・IRをカットする熱線吸収ガラスを使用し、カーテンの設置は省略している。窓ガラスは車端部は固定窓だが、各ドア間の大窓は非常時の換気を考慮して、下降窓と固定窓の組み合わせとなっている。
本系列の優先席部は一般席との区分を明確にするため、壁面をクリーム色に、床材を赤色格子模様とした。従来の車両と同じく座席表地を赤系の斜めストライプとし、つり革はオレンジ色品、握り棒については黄色のラバー仕上げとした。さらに優先席を含む両車端部の3人掛け座席部においては荷棚とつり革高さを 50 mm 低くしたものとした。また、各番台区分とも編成中の一部車両においては、すべての荷棚とつり革を優先席と同じ 50 mm 低くした仕様を採用した。
冷房装置は集中式のAU726形[6](3000番台のグリーン車を除く)で、出力は 58.14 kW (50,000 kcal/h) を各車両に搭載する。車内の臭気対策としてJR東日本の一般形電車で空気清浄機を初めて搭載しており、集塵機能と脱臭機能がある。なお、空気清浄機はJR・私鉄の多数の形式にも追加で搭載された。
山手線用のE231系500番台と同様に、自動放送装置や、車内の各客用ドア上部に液晶ディスプレイ(LCD・トレインチャンネル・VIS)2基(2000番台は1基、3000番台は2段式のLED文字スクロール表示式)を用いた車内案内表示装置を設置している。 自動放送は、全編成で音声を三浦七緒子(日本語)とクリステル・チアリ(英語)が担当しており、急停車時に「急停車します。ご注意ください」と注意を喚起する放送もある。平日のラッシュ時間帯(7時~9時30分と17時~19時30分)および終電時間帯(23時以降)には乗り換え案内などが自動で省略される。
走行機器など
車両の性能についても改良を加えた。また、故障や事故などに備えて同一機器を2基以上搭載(パンタグラフ・空気圧縮機 (CP) ・MT比を上げることでの主回路機器の個数増など)したり、二重化(モニタ装置の伝送・演算部や保安装置・補助電源装置 (SIV) など)を施し、万一片方が故障しても自力走行ができるように、他の鉄道事業者でも一般的となりつつある二重化設計思想がJR東日本の車両として初めて採用された(冗長化)。
本系列においてもE231系で採用した列車情報制御システム”TIMS”(Train Information Management System)を採用しているが、システムは伝送速度の向上(2.5 Mbps → 10 Mbps)や二重系化を図ったものへと改良している。
主制御器は64ビットマイコンとIGBT素子を使用した2レベルVVVFインバータ制御方式である。装置の形式はSC85で三菱電機製であり、質量は828kgとなっている (3000番台を除く) 。電動機制御は1C4M2群構成である。主電動機は出力140kWのMT75形を採用した。歯車比はE531系と同一の 1:6.06 である。
起動加速度は 2.3 km/h/s 、2.5 km/h/s 、3.0 km/h/s が選択可能で、それぞれの運用路線に応じて設定される。ただし、2000番台は地下鉄線内の協定から 3.3 km/h/s とやや高めに設定されている。
補助電源装置はIGBT素子を使用した静止形インバータ (SIV) とし、形式はSC86となっており(東芝製)、質量は1545kg、出力電圧は三相交流 440 V 、電源容量は 260 kVA と大容量を誇る (2000番台を除く) 。このSIVは制御回路等を2台有する「待機2重系」のシステムを採用しており、片方の系統に故障が発生した場合、もう片方の系統が機能することで冗長化が図られるものである。
空気圧縮機 (CP) はE531系で新規開発されたスクリュー式のMH3124-C1600SN3形式を採用している。集電装置はシングルアーム式のPS33D形パンタグラフであるが、常時使用しているパンタグラフの他に、編成で1台は予備のパンタグラフ (通常走行時は折りたたんだ状態) を搭載している。万が一、常用のパンタグラフがすべて使用不能の場合にも1ユニットが使用できるようにされている。
ブレーキ制御は回生ブレーキ併用の電気指令式空気ブレーキで、常用ブレーキについてはTIMSを介した編成単位でのブレーキ制御を行うものである。このほか、直通予備ブレーキ、降雪時に使用する耐雪ブレーキ、0番台と3000番台のみ勾配区間用の抑速ブレーキを有する。
台車は、制御車(クハ:Tc, Tc')と付随車(サハ:T)がTR255形およびTR255A形、電動車(モハ:M、M')がDT71形を装着する。方式は209系以来の軸梁式ボルスタレス構造である。最高速度が 120 km/h であることから通勤タイプではヨーダンパは省略したが、軸バネオイルダンパを装備して縦方向の揺れであるピッチングを緩衝している。ただし、3000番台では全車両にヨーダンパを装着している。
3000番台
国府津車両センター向け車両
東海道本線を走行する国府津車両センター所属の3000番台 E01+E51編成。
JR東日本では、2007年度から鎌倉車両センター配置で、横須賀線・総武快速線で運用されているE217系のVVVFインバータ装置などの機器類更新工事を開始した。更新工事の施工に際して、鎌倉車両センターに配置されている予備編成が不足することから、2006年(平成18年)に
東海道線・伊東線で運用していた113系を置き換えるために国府津車両センターに転属したE217系基本10両+付属5両編成1本を再度鎌倉車両センターに配置することとなったが、その補充分として製造されたのが本系列の近郊タイプとなる3000番台である。
2007年(平成19年)に東急車輛製造で基本10両+付属5両1本が落成し国府津車両センターに配属、同年11月27日から28日にかけて試運転が実施された。当初は2008年(平成20年)3月7日より営業運転を行う予定だったが、同日に人身事故が発生したため延期となり、3月10日から東海道本線で営業運転を開始した。
その後、2010年(平成22年)2月に第2編成としてE02編成+E52編成が落成した。この第2編成は2010年3月13日のダイヤ改正における横須賀線武蔵小杉駅開業に伴って同線の増発が行われることとなり、東海道線で運用してきたE217系1編成(基本10両+付属5両)を再度横須賀線に転用するための捻出用として製造された。
田町車両センター向け車両
東海道線を走行する田町車両センター所属の3000番台。NT3+NT53編成
2011年度(9月以降落成・NT1編成とNT51編成 - )からは東海道線、東北本線・高崎線系統で運用している211系の後継車種として田町車両センターにも配置が開始されており、先に落成していた国府津車両センター向けの車両から編成形態が一部変更されている
。これは基本編成の6号車にもトイレ付き車両を連結するためで、新たにモハE232形3800番台が連結された。車内の車端部には一般洋式のトイレが設置され、反対側には枕木方向に2人掛け座席が設置されている。
従来の国府津車両センター向け車両では、6号車に補助電源装置(SIV)搭載のモハE232形3000番台を連結していたが、田町車両センター向け車両の6号車には汚物処理装置を搭載したため、SIVの搭載ができなくなり、国府津車両センター向け車両と比べ一部の電動車(モハ)の連結位置が変更されている。また、モハE232形3200番台は非連結とされた。なお、付属編成については特に編成の変更はされていない。このほか、基本編成
+ 付属編成の併結運転時に、車両間からの転落事故を防止するために10号車のクハE233形3000番台には転落防止放送装置を設置した。
基本的には国府津車両センター車両の続番となっているが、編成内で車両番号を統一するため、モハE232形3800番台は3801・3802号車が欠番となっている。この田町車両センター向け車両は2011年11月12日から営業運転が開始されている。今後、2012年(平成24年)4月頃までに基本・付属編成とも14編成(210両)が投入される予定で、田町車両センター所属の211系は同年5月末までに全て置き換えられる予定となっている。
田町車両センター向けの車両は新津車両製作所で製造している(グリーン車は東急車輛製造製)。これらの車両は2013年度末に開業が予定されている東北縦貫線開業に向けて導入を進めているもので、東北縦貫線開業までに、田町車両センター投入分のほか、更に16編成を加えた計30編成が投入される予定で、これにより田町車両センター・高崎車両センター所属の211系が置き換えられる予定である。
国府津車両センター向け車両のVVVFインバータ装置は、先に落成していた0番台・1000番台に採用された三菱電機製のSC85形系列とは異なり、本番台には日立製作所製のSC90形が採用されている。MT比は基本編成が
6M4T 、付属編成が 2M3T と、同様に運用されるE231系近郊形よりも上がっているが、起動加速度はE231系に合わせた 2.3 km/h/s
に設定されている。
田町車両センター向け車両では新規に開発したSC98形が採用されており、SC90形よりも小形軽量化および信頼性の向上が図られている。また、E231系と本系列はシステムが異なるが、TIMSにはE231系と併結した際に相互のインタフェースを図る併結読み替え機能が追加されている。
台車はE233系では初めて普通車を含む全車両にヨーダンパが設置された。保安装置はE231系近郊形と同様にATS-P形と東海旅客鉄道(JR東海)エリアへの入線に対応する速度照査機能付ATS-SN形を搭載する。
仕様
車体の帯色はE231系近郊タイプと同一の「湘南色」であり、編成形態もE231系近郊タイプに準じたもので、基本編成となる10両編成と付属編成となる5両編成で構成される。基本編成の4・5号車には2階建てグリーン車が連結されている。客室設備については基本的に通勤形に準じた仕様である。
普通車の座席はロングシートが基本であるが、基本編成両端の2両(1・2・9・10号車)と付属編成の東京方2両(14・15号車)はセミクロスシートを配置している。車椅子スペースは各先頭車に配置しているほか、ロングシートの先頭車(11号車)においてはすべての荷棚とつり革を50mm下げた優先席と同仕様のものとした。
トイレ設備は10両編成の両端先頭車(1・10号車)と付属編成の熱海方先頭車(11号車)の連結面側に電動車椅子対応の大型トイレ(真空吸引式洋式)を設置した(田町車両センター向けは6号車にも一般用トイレを設置)。出入口の開口幅はE231系より広い 850 mm だが、E531系のような変則的なドア配置にはしていない。車内案内表示器は通勤形と異なり、LEDによる2段式の文字スクロール表示式をドア上部に設置している。
ドアエンジンはE233系としては初めてのリニアモーター駆動式となり、さらに0番台同様に半自動機能と3/4閉機能を有する。
グリーン車
近郊仕様となる3000番台では2階建てグリーン車を2両連結する。設計自体はE231系やE531系で運用されている車両に準じたものである。
車両は両端部が平屋構造となり、車体中央部が2階建て構造となっている。座席はすべて回転式リクライニングシートを配置している。座席は平屋部と1階部が赤紫系色、2階部が青系色となっている。また網棚は平屋席のみに設置されている。その他グリーン車Suicaシステムに対応させるため各座席の天井部にはSuica(相互利用ができるICカードを含む)をタッチするための装置(R/W〈リーダ/ライタ〉)が取り付けられ、各座席のテーブルにはSuicaシステムの利用方法の案内ステッカーが貼られている。客用ドアの室内側はステンレス無塗装仕上げとし、ドアガラスは単板ガラスを接着方式で固定するものである。
サロE233形3000番台には熱海方のデッキに洋式トイレと洗面所を備え、サロE232形3000番台の東京方のデッキには乗務員室と業務用室(グリーンアテンダントの準備室)を設置する。また業務用室には車内販売に対応させるため冷蔵庫やコーヒーメーカーなどが設置されている。これらの車両の冷房装置は出力
23.3 kW (20,000 kcal/h) のAU729形を2台を搭載する。
東海道線で女性のグリーンアテンダントへの暴行事件が多発したため乗降口(デッキ)と乗務員室・業務用室前に防犯カメラが設置された。
走行機器
国府津車両センター向け車両のVVVFインバータ装置は、先に落成していた0番台・1000番台に採用された三菱電機製のSC85形系列とは異なり、本番台には日立製作所製のSC90形が採用されている。MT比は基本編成が 6M4T 、付属編成が 2M3T と、同様に運用されるE231系近郊形よりも上がっているが、起動加速度はE231系に合わせた 2.3 km/h/s に設定されている。
田町車両センター向け車両では新規に開発したSC98形が採用されており、SC90形よりも小形軽量化および信頼性の向上が図られている。また、E231系と本系列はシステムが異なるが、TIMSにはE231系と併結した際に相互のインタフェースを図る併結読み替え機能が追加されている。
台車はE233系では初めて普通車を含む全車両にヨーダンパが設置された。保安装置はE231系近郊形と同様にATS-P形と東海旅客鉄道(JR東海)エリアへの入線に対応する速度照査機能付ATS-SN形を搭載する。
(ウィキペディアより引用)
MTR
(Mahora-Transportation-Railway) 麻帆良学園都市鉄道
![]()
■●基本A 5両セット【92375】+基本B 5両セット【92376】+増結 5両セット【92377】
■近郊形に合わせ、セミクロスシートを再現(1、10号車)
■近郊形に合わせ、セミクロスシートを再現(14、15号車)
■前面の行先・種別表示部は交換式で交換選択用表示パーツ付属
■運行表示番号も白色LEDで実感的に点灯
■動力車モハE233-3000は予備パンタ付の車両
■フライホイール付動力、新集電システム、黒色車輪採用
■車番は転写シール対応
■JRマーク印刷済み
![]()
■クハE233-3000前面側はTNカプラー(SP)装備
■クハE233-3500前面側はTNカプラー(SP)装備
■トイレ付先頭車クハE233・232-3000を新規製作
■トイレ付先頭車クハE232-3500を新規製作
■ヘッドライト白色LED、ON/OFFスイッチ付き
■主な材質 本体:ABS樹脂、ケース:PP
![]()
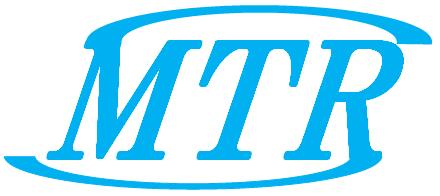








 基本セットAのクハE233-3000および基本セットBのクハE232-3500の前面側はTNカプラー(SP)装備。
基本セットAのクハE233-3000および基本セットBのクハE232-3500の前面側はTNカプラー(SP)装備。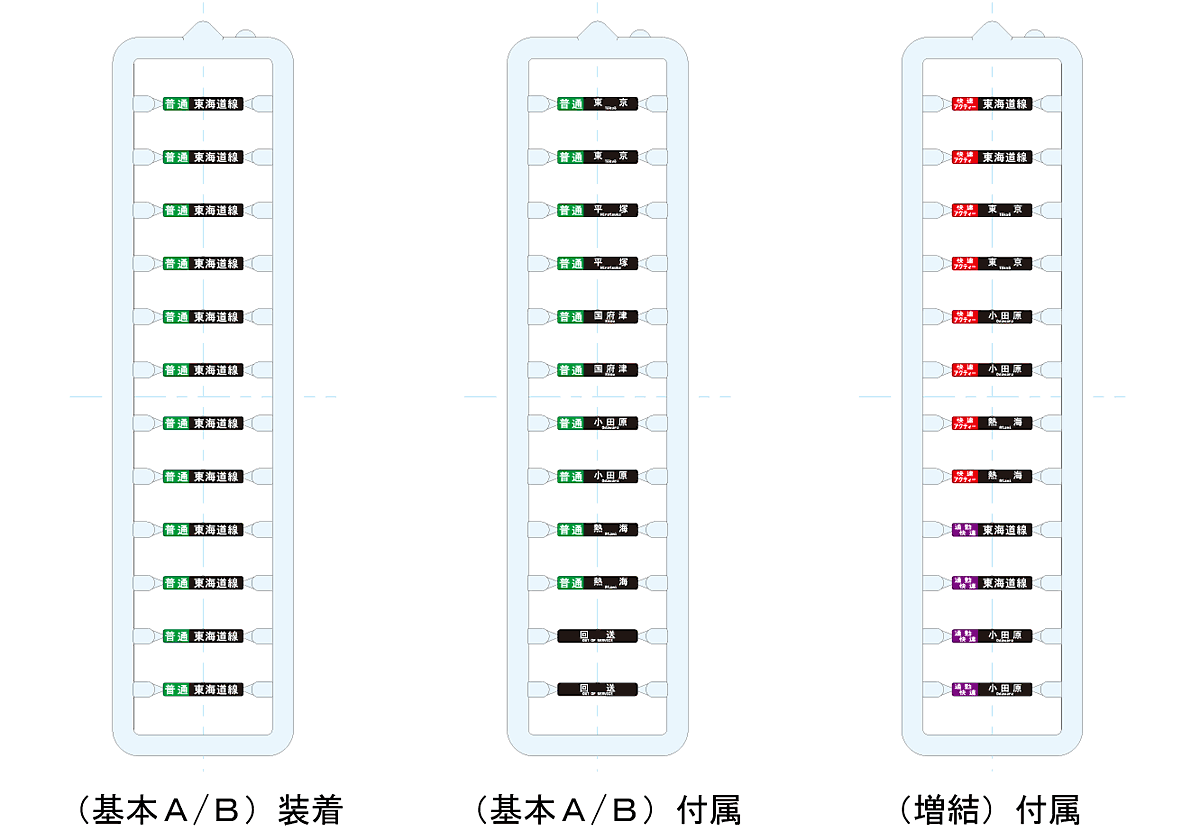 前面の行先・種別表示部は交換式で交換選択用表示パーツが付属。
前面の行先・種別表示部は交換式で交換選択用表示パーツが付属。
 1・2・9・10・14・15号車はセミクロスシートを再現しています。
1・2・9・10・14・15号車はセミクロスシートを再現しています。 4・5号車のグリーン車サロE232-3000、サロE233-3000は実車に則して階下席のシートを赤系で、
4・5号車のグリーン車サロE232-3000、サロE233-3000は実車に則して階下席のシートを赤系で、 屋根上のクーラーはAU726Aを搭載。東急車輌製をプロトタイプとし、屋根上のリブは細いタイプを再現しています。
屋根上のクーラーはAU726Aを搭載。東急車輌製をプロトタイプとし、屋根上のリブは細いタイプを再現しています。  台車はダンパが追加された姿のDT71を新規製作で再現しています。
台車はダンパが追加された姿のDT71を新規製作で再現しています。